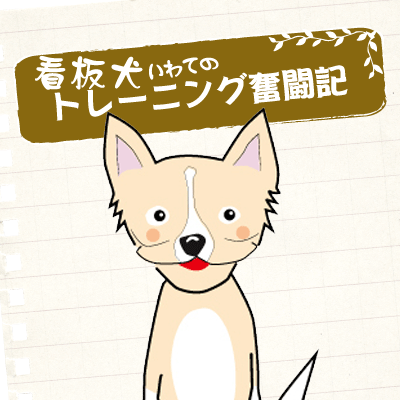「本町獣医科サポート」の獣医師 北島 崇です。
近年、動物医療の進歩やフード・サプリメントなど栄養面の充実などによりペットの寿命は延びてきました。
これに合わせて腫瘍やがんの発生も増加し、がんはペットの死因第1位になっています。
今回は愛犬の腫瘍・がん治療ついて知って頂こう考えます。

目次
ペットのがん
私たち動物のからだをつくっている細胞は、規則正しいサイクルで「生まれて死んで」を繰り返しています。
いわゆる新陳代謝です。
しかし、いろいろな理由からこのサイクルが狂ってしまい、無秩序に細胞が増殖することがあります。
これが腫瘍であり、その中の悪性の腫瘍の1つをがんと呼んでいます。
がん治療の目的
現在では、「がん=不治の病」というイメージはだいぶ無くなってきました。
早期発見・早期治療により、がんも十分完治する病気になりましたが、ヒトとペットではがん治療の目的が異なります。
ヒトのがん治療の目的は「延命」すなわち生存期間の延長です。
このため、入院して何度も手術を行ったり、強い副作用がある抗がん剤も使用されます。
これに対しペットの場合は、「QOL(生活の質)の維持」が主眼となります。
できるだけ入院は避けて、薬による副作用も最小にし、苦痛を和らげる対処が求められます。
オーナーのみなさんの考えはどうでしょうか?

発生しやすい部位
イヌにおいて腫瘍・がんが発生しやすい身体の部位や品種にはどのようなものがあるのか確認しましょう。
岐阜大学の駒澤 敏がイヌの腫瘍3,985例をもとに調査した結果があります(2016年)。
○皮膚とその周辺組織の腫瘍(30.9%)
…パグ、ゴールデン/ラブラドールレトリバー
○消化器系の腫瘍(18.4%)
…口腔内や肛門周囲を含む
…シュナウザー、シーズー
○乳腺腫瘍(18.0%)
…ダックス、キャバリア、パピヨン
○その他の部位(32.7%)
ここで記載した数値は良性悪性をまとめた腫瘍発生率です。
悪性腫瘍の発生率が高い犬種としては、ラブラドール/ゴールデンレトリバー、コーギー、ビーグルなどがあるようです。

がんの治療方法
ドラマで腫瘍・がんの治療場面を見ると手術をしたり、抗がん剤を使ったりしています。
ペットの場合もヒトと同様で、次の3つの治療方法(外科療法、放射線療法、化学療法)があります。
外科療法
外科療法とは手術によって腫瘍・がんの病巣を切除するものです。
しっかりと切り取ることができれば最も有効な処置になります。
この場合、全身麻酔を行いますので、ペットの年齢体力なども考慮に入れる必要があります。
また、病巣と正常部位との境界が明瞭でなかったり、脳の深い部位など安全に手術できない場合があります。
このような場合はメスを用いた外科療法は行えないため、放射線療法や化学療法が実施されます。

放射線療法
放射線療法の放射線とはレントゲン検査のX線のことです。
レントゲン検査よりも強力にしたX線を細胞に照射すると遺伝子が傷つき、細胞分裂=増殖ができなくなります。
これを腫瘍・がん治療に応用したものが放射線療法です。
腫瘍・がん細胞は無秩序に細胞分裂を起こし増殖します。
したがって、正常な細胞と比べるとX線に対する感受性が高く、受けるダメージも大きいことになります。
脳の腫瘍など外科手術ができない部位の治療に適しています。
放射線療法は切らずに処置できるというメリットがありますが、全身麻酔は必要です。
また1回の照射で完了せず何回が実施して、ターゲットである腫瘍・がん組織をゆっくりジワジワと小さくしてゆく治療になります。
このように放射線療法は一部にまとまった腫瘍・がん組織にはピンポイントで照射できますが、全身に広く転移してしまっている場合では採用できません。
このような時に実施されるのが化学療法です。

化学療法
化学療法とは薬剤の投与による治療のことで、抗がん剤がこれにあたります。
化学療法が実施されるのは、白血病など全身性の腫瘍(=限定した病巣がないもの)や他の部位に転移した悪性度の高いがんの場合などです。
抗がん剤は点滴により投与され全身に作用します。
抗がん剤と聞くと、腫瘍やがんだけを狙ってやっつける薬といったイメージがありますがこれは間違いです。
抗がん剤には遺伝子に影響してタンパク質の合成などを阻害することにより、細胞を縮小・死滅させるという作用があります。
したがって腫瘍・がん細胞であれ正常細胞であれ、抗がん剤のターゲットは活発に増殖しているすべての細胞です。
加えて抗がん剤は点滴で投与されるため、全身の細胞が影響を受けることになります。
抗がん剤ががん組織に作用しこれが小さくなると「効果」と評価されます。
これに対して、正常細胞が影響を受けた時は「副作用」と呼ばれます。
消化器系がダメージを受けると食欲低下や嘔吐、骨髄なら免疫系細胞の減少による細菌感染や発熱などが副作用として現れます。

愛犬のがん
最後に愛犬の腫瘍・がんとして比較的よく知られているものを2つ紹介しておきます。
肥満細胞腫
イヌの皮膚や皮下に発生する悪性腫瘍に肥満細胞腫というものがあります。
肥満細胞というのはからだの免疫を担当している細胞で、炎症やアレルギー反応などに関与しています。(肥満細胞と脂肪細胞は別物です)
正常な肥満細胞はヒスタミンという炎症の引き金になる物質をもっており、肥満細胞腫にも蓄えられています。
肥満細胞の腫瘍化によりこのヒスタミンが大量に放出されると、周囲の組織に炎症が発生したり、胃潰瘍やショック状態などを引き起こされます。
肥満細胞腫の治療方法を確認しましょう。
○外科療法
…他の部位へ移転しておらず限局しているものは手術で除去できます。
○放射線療法
…肥満細胞腫はX線に対する感受性が高いため有効です
○化学療法
…放出されるヒスタミンによる炎症を抑える目的として、ステロイド剤が
投与されます
…抗がん剤も有効ですが副作用を伴う可能性があります

乳腺腫瘍
愛犬の腫瘍・がん発生部位として3番目に多かったのが乳腺腫瘍(18.0%)でした。
乳腺腫瘍は女性ホルモンの影響により、乳腺の細胞が腫瘍化するものです。
乳がん(=悪性腫瘍)と異なり、乳腺腫瘍のおよそ50%は良性です。
残り半分の内、25%は悪性ですが外科手術により根治可能といわれています。
そして残り25%が他の部位に転移したり、処置しても再発の可能性が高い悪性腫瘍になります。
結論として、乳腺腫瘍全体の75%は外科手術により根治可能であるといえます。
乳腺腫瘍の大きさと生存率・根治率との間には、おおよそ次のような関係があります。
○1cm 未満 …長期生存率 100%
○1~3cm …根治率 約80%
○3cm 以上 …根治率 約60%
腫瘍サイズが大きくなるほど予後が悪くなってゆきます。
腫瘍・がんに限らず、定期検診による早期発見・早期治療が大切であることがよく判ると思います。
先ほど乳腺腫瘍は女性ホルモンが関与していると述べました。
避妊手術の実施の有無と乳腺腫瘍の発生割合の関係を見てみましょう。
○避妊を初回発情前に行っている場合
…200頭に1頭の割合で発生(約0.5%)
○避妊を行っていない場合
…4頭に1頭の割合で発生(約25%)
このようにイヌの乳腺腫瘍は幼い時期の避妊手術により、発生予防が可能な腫瘍であるといえます。

今回はおおまかに愛犬の腫瘍・がんの治療方法を紹介しました。
大きく3つの方法がありましたが、その中でオーナーのみなさんが一番に気になるのが化学療法/抗がん剤による副作用ではないでしょうか?
次回はペットの抗がん剤の副作用と自宅ケアを行う際の注意点を解説します。
(以上)
帝塚山ハウンドカムのネットショップ
執筆獣医師のご紹介

本町獣医科サポート
獣医師 北島 崇
日本獣医畜産大学(現 日本獣医生命科学大学)獣医畜産学部獣医学科 卒業
産業動物のフード、サプリメント、ワクチンなどの研究・開発で活躍後、、
高齢ペットの食事や健康、生活をサポートする「本町獣医科サポート」を開業。